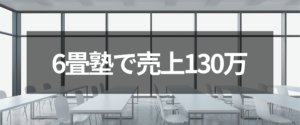どーも、きくらげ鰹です。
本ブログについて
高専専攻科を卒業後、少子高齢化が深刻な人口10万人ちょいの片田舎で、就職もせずに個人塾を開業したきくらげ鰹(カツオ)が書くブログ。金なし・社会人経験ゼロで起業したため、開業時から失敗しまくり。運だけはいいので、従業員ゼロ・家賃3万(笑)のアパート塾で気付けば月収100万(月商130万)の塾に成長。過去の自分へ向けて『月収100万円の安定収入を確立し、満員御礼を継続するための小ネタやノウハウ』をまるでメッセージを送るかのようにして記事を執筆中
「さあ、塾をつくろぞー」意気込んだあとに悩むのが
まず、どこに塾を作るか
すなわち、塾や教室の立地問題です。
塾だけではなく、飲食店・美容室・マッサージ屋さん、どのビジネスにおいても立地戦略は集客のキモです。
飲食店を例に挙げても、
おしゃれで一等地にある店=売り上げが上がる店
ではありません。
例えば、ご高齢者が多い街だと、ご高齢者が来やすいような場所にあり、雰囲気が居心地が良く食べ物や味のの店が繁盛していますよね。
「立地を制するものは集客を制する」
塾・教室にも立地戦略がありますので、本記事ではきくらげが考える塾の立地戦略について解説します。
※ 立地戦略は地域柄の影響をもろに受けますので、あくまでもきくらげが考えることについて書いています。
※ 自宅教室を指導を考えられている先生にも有益な記事であるかと思いますので、ぜひ読んで欲しいなと思います♪
ターゲットによって意識することが変わる
まず学習塾を運営する際は、どの年齢層の生徒を対象とするかを明確にすることがとても重要です。
最近では、小学生や中学生、高校生だけでなく、幼児を対象にした塾も増えていますよね。
そのため、どの層に特化するかを最初にしっかり決めましょう。
ターゲットを広く設定すると、生徒がたくさん集まりそうに感じるかもしれませんが、実際には専門性が薄い印象を与えることがあります。
たとえば、「中学受験に特化した塾」や「高校受験に強い塾」といった専門性を打ち出すことで、塾の魅力が伝わりやすくなりますよ。
ちなみに、都会や都市部の場合はターゲットを絞り、地方の場合はややターゲットが広めの方がいいような気がします。

田舎の場合はターゲットは狭すぎても広すぎてもダメです。
では、まず塾を出す際に意識する項目について解説します。
塾を出す際の意識する項目
学習塾や教室を作る際の検討項目として、
- 学校数
- 市や町の生徒人口
- 学校間の距離
- 地域の治安
- 地域柄 (教育に熱心な地域かどうか)
- 流動人口
- 親の教育費への意識や支出傾向
- 競合塾や教室の数・内容
- 公共交通機関や駐車場の利便性
どの項目を優先するかは、対象となるターゲット層や塾のコンセプトによって変える必要があります。
たとえば、中学受験を目指す生徒をターゲットにする場合、地域柄や教育熱心な家庭が多いかどうかが重要になります。一方、高校生、大学生、社会人やシニア向けの教室では、交通アクセスの良さや流動人口の多さが重要な要素となります。
また、競合する塾や教室がどのようなサービスを提供しているかを調査し、差別化ポイントを明確にすることも欠かせません。これらの検討項目を総合的に考慮し、ターゲット層に最適な立地や運営方針を決めることが、集客のしやすさに直結します。
今回は学習塾がターゲットにする小学生・中学生・高校生に絞ってた最適な立地について解説します。
小学生・中学生の学習塾の場合
小学生や中学生をターゲットにする塾・教室の場合は、
- 学校から近い
- 通学路
- 住宅街
が良いかなと思います。
学校帰りや家に帰ってからそのまま自転車で塾に来れますらかね。
きくらげが小学生の頃に通っていた公文は住宅街に、中学校の時に通ってた個人塾は住宅街に、高校生の時に通ってた個人塾も住宅街にありました。
住宅街にある=学校から近い
ので、
まず小学生・中学生をターゲットにする場合は住宅街や学校の近くの物件を検討すると良いでしょう。
よくよく考えると、小学生・中学生を対象にしている塾の多くは学校の近くや住宅街にあるケースがほとんどではないでしょうか?
※ あくまでも田舎での話ですがね...
治安が良い場所に塾を出す
特に徒歩や自転車で塾に通塾する小学生や中学生が多い塾は、地域の治安の良さも検討項目になります。
生徒たちの安全は塾にとって、一番考えないといけない事項です。
治安が良い地域には教育熱心なご家庭が住んでいる可能性が非常に高いです。
治安の良い地域に出すことで入塾率が高まる可能性もあります。

育った街に塾を出店する場合はどの地域が治安が良くてどの地域が治安が悪いのかが分かりますよね。もし育った地域外で塾を出店するのであれば、不動産屋さんに相談してみると良いでしょう。
最近は小学生た中学生が痛ましい事件に巻き込まれているのを報道しているニュースであっていますよね。
極力、治安の良い地域に塾は出店するようにしましょう。
高校生向けの学習塾の場合
高校生をメインターゲットした塾・教室の場合は、高校生の流動が多い駅近くが良いです。
高校生をメインターゲットにする場合は、学校数よりも高校生の流動人口の方が大事です。
流動人口とは特定のエリアに短期間だけ訪れる人々を指し、その地域に常住していないものの、一時的にその場所を利用したり滞在したりする人々を含みます。
流動人口の動向は、商業施設や店舗の集客力、公共交通の利用状況、観光地の人気度などに大きな影響を与えます。
学習塾にとっての流動人口=高校生の流動人口
です。
高校生をメインターゲットにすると、別の地域から通学する生徒を集客することができるのです。
高校は駅の近くにあったり、駅からバスが出ていたりしますので、高校生をターゲットにする場合は、バスの数なども調べておくといいですね。
駅近に塾を出すのはもちろんのこと、高校と駅の通学路に塾があるのかどうかも大切です。
少し外れてもいいのですが、駅から高校まで自転車で通う高校生も多いです。
駅と高校の間に塾があると尚よしです。

きくらげの塾は高校生比率が50%です。そのため、他の市や県から通う塾生も多いです。高校生をメインターゲットにすると、自然と中学生や小学生も集客することができますよ
話が脱線しますが、
個人塾で高校生までターゲットにすると、指導がとても大変です。
中学生・小学生の指導に比べたら高校生の科目を指導する負担はざっと3~4倍ほど。
それほど、高校レベルの科目を指導するのは大変です。
その分、うま味はありますが....
あえて競合の近くに出す
あえて、競合の近くに出すのもアリです。
特に、駅周辺は
- 東進ハイスクール
- 明光義塾
- 個別指導のトライ
- 武田塾
- 英進館
- 全教研
- 栄光ゼミナール
- 早稲田アカデミー
などの大手学習塾が集まっており、どこも潰れていないということは
その周辺地域に塾を出せばそれなりに集客ができる目安になります。
きくらげの塾も周辺に8つくらい学習塾が乱立していていて、塾激戦区にあります。
駅周辺でも8つほど学習塾があり、駅から半径3kmくらいに広げると、15つくらいの学習塾があります。
塾をやり始める前は、競合がいない地域に塾を出した方がいいのでは?
と考えますが、
塾がない地域=需要がない
のかもしれません。
もし、塾がない地域に出店を考えている場合は、
「なぜ、この地域は塾がないのか?」
をきちんと分析をした方がいいです。
考えれば自ずと答えが見つかります。
塾がないのはないなりの理由がありますから。
もし、指導力や仕組み、サービスの質に自信があるならば、思い切って塾激戦区に塾を出す方が集客できます。

塾激戦区に塾を出しても、webマーケとクチコミで満員状態にすることができます。満員と書いていますが、一人で塾で約100名ほどの塾生を抱えていますので、一人塾の割には少ない人数ではないのかなと思います。
大手学習塾や予備校がいくつかあるかどうかが、その地域に塾を出した方がいいのかの指標になりますよ。
きくらげの物件契約の時の体験談
かれこれ数年以上になりますが、きくらげが物件を決めた時の体験談について話そうかなと思います。
今のアパートに移転する前は、
間借りで塾で塾を運営していましたので、ぜひその時の記事もお読みください。
一軒目は微妙...
移転を決めたのが、間借りで塾で塾生が集まり始めた年の8月後半です。
物件を借りるためにはまずは不動産屋さんに相談をしないといけないのですが、
きくらげファーザーに大工の知り合いがいたので、大工さん経由でまず一つ目の不動産屋さんを紹介してもらいました。
不動産屋さんに
- 駅近
- 家賃4万以下
- 商用利用OK
と伝えてると、
いくつか候補を出してくれたのですが、

なんか、しっくり来ないな...ここ周辺の物件がいんだけどな
あまり、しっくり来ず。
不動産屋さんにGoogleマップを見せながら、
「ここら辺に物件ないですか?特に、この建物がいいです。ここがいいです。どうしてもここがいい。」
と無理難題を伝えたら、
知り合いの大工さんが、
「そこなら、〇〇不動産が物件持ってるかも」
と
〇〇不動産にすぐに電話をしてくれました。
最後は直感
大工さんが、〇〇不動産に電話すると
「その物件持ってますよ。塾での利用ですか?あーいいですよ」
と二つ返事で物件の候補が決まりました。
一軒目の不動産屋さんを後にして、二軒目の〇〇不動産に出向き、
〇〇不動産さんの社長ときくらげが希望する物件に行きました。

あーここだ
と直感で感じたので、
「ここがいいです」
とすぐに伝えました。
そしたら、不動産屋さんが、
「まだ、いくつか物件あるけど、本当にここでいいの?」
と質問されたので、
「ここでお願いします」
と答え、すぐに物件の契約をお願いしました。
そこからは、
- 審査
- 家具の購入
- 内装屋に壁紙の発注
- 移転作業
の全てを2週間で行いました。
間借りで塾に通ってくれている塾生にも「塾が移転したよ」と伝え、移転作業がスムーズに終わりました。
縁がある時って、とことん現実が進んでいくんですよね...
人生って本当に不思議です。
ちなみに余談にはなりますが、
きくらげが移転した物件は元々公文をする予定の人が入るか検討中だったとのことでした。
狭いのが理由で「なし」になったとのこと。
「ラッキーでした」
今回の記事を整理
塾や教室の立地は、
どの層をメインターゲットにするかでどの場所で塾や教室を運営するかが変わってきます。
きくらげの意見ですが、
小学生・中学生 : 学校近くや通学路・住宅街
高校生 : 高校生の流動人口が多い駅近く
駅と高校が通学路
というポイントも忘れてはいけません。
例え、少子高齢化が深刻な街であっても、
学習塾が乱立しているような街であれば、塾需要が高いので、子供たちの出生数などはあまり気にしなくていいのかもしれません。
きくらげの塾がある街がまさに、少子高齢化が著しく進んでいる街です。
にもかかわらず、学習塾がどこも潰れない
まさに塾タウン。
物件の地域が決まった後は、実際の物件選びですが、
諸々の条件を提示した後に不動産屋さんからいくつか物件の候補を提示されます。
物件選びは最後は直感です。
自身がその場所で指導してるイメージが湧くかどうか
こういうのってとても大切だときくらげは思います。
今回の記事がみなさまのお役に立てば幸いです。
今回の記事はここまでです。