どーも、きくらげ鰹です。
本ブログについて
高専専攻科を卒業後、少子高齢化が深刻な人口10万人ちょいの片田舎で、就職もせずに個人塾を開業したきくらげ鰹(カツオ)が書くブログ。金なし・社会人経験ゼロで起業したため、開業時から失敗しまくり。運だけはいいので、従業員ゼロ・家賃3万(笑)のアパート塾で気付けば月収100万(月商130万)の塾に成長。過去の自分へ向けて『月収100万円の安定収入を確立し、満員御礼を継続するための小ネタやノウハウ』をまるでメッセージを送るかのようにして記事を執筆中
塾や教室の開業時に
塾や教室のお問い合わせ手段を考えないといけません。
お問い合わせ手段としては、
- 固定電話
- 携帯電話
- webお問い合わせ
- メール
- LINE
- SNS
などがありますが、どのお問い合わせ方法を導入するといいのでしょうか。
特にどのお問い合わせがオススメというのはありませんが、きくらげの塾で導入しているお問い合わせ方法について解説して行こうかと思います。
お問い合わせのしやすさも入塾につながる大事な部分です。
保護者の方がお問い合わせしやすいような仕組み作りをしていきましょう。
お問い合わせ方法の導入時は二軸で考える
お問い合わせ方法の導入時には
① 保護者にとってお問い合わせがしやすい方法
② 自分がやりとりしやすい方法
の両方を満たすのを選べば良いです。
きくらげにとっては、
① 保護者にとってお問い合わせがしやすい方法
② 自分がやりとりしやすい方法
を満たすのが公式LINEの導入でした。
チャットですので、指導の合間に返信ができまずし、文面に落とすので食い違いもありません。
ですので、塾のホームページの目立つところに公式LINEのリンクは掲載して、「可能なら公式LINEでのお問い合わせをお願いします」のような一文を入れています。
その結果、全お問い合わせの5割以上は公式LINEからのお問い合わせになっています。
また、他のお問い合わせ方法、例えば電話やメールでお問い合わせいただいた方にも公式LINEへのご登録をお願いすることで、入塾面談・体験のやりとりはほとんど公式LINEで完結させています。

自分がどう仕事をするとやりやすくなるのかを考えることは大事ですよね
きくらげの塾で導入しているお問い合わせ方法
先ほど、公式LINEを導入しています
と書きましたが、実はきくらげの塾ではいくつかお問い合わせ方法を用意しています。
次にきくらげの塾で導入している方法について解説しますね。
きくらげの塾では5つのお問い合わせ方法を導入しています。
- 固定電話
- webお問い合わせ
- メール
- LINE
- SNS
公式LINE
先ほども書いたようにきくらげの塾のお問い合わせ方法として一番多いのが公式LINEへのお問い合わせです。
多くの方がLINEを使っていますからね。
2023年度の調査によると、LINEの利用率は83.7%であり、10代から60代までの全年代で8割を超えています。
また、70代でも7割以上の利用率となっています。
きくらげが公式LINEを活用している理由は
- 塾内連絡用にLINEを使っているため、使い慣れてるから
- メッセージが一覧で出てきて把握しやすい
- 文字に残すためミスを減らせる
- 指導の合間に返信することができる
ためです。
電話だとどうしても入塾面談の予約日時などを間違ったりしてしまいそうで...
ですので、公式LINEを活用しています。

友達登録者数が表示されるため、登録者数が多いと人気の塾かな?と思ってもらえそうというのもLINEをメインの連絡手段に使っている理由です。
HPお問い合わせフォーム
まれにホームページのお問い合わせフォームからもお問い合わせをいただきます。
公式LINEを導入する前まではほとんどのお問い合わせがHPのお問い合わせフォームでした。
保護者の方にとってもお問い合わせしやすいお問い合わせ方法だと思います。
こんな感じのお問い合わせフォームを塾のHPに設けています。

ちなみに、このお問い合わせフォームには業者からの営業のお問い合わせもきます。
営業の連絡はフル無視しています笑
固定電話
固定電話を導入する前までは携帯電話をHPに掲載していました。
きくらげの塾が田舎にあるためか、固定電話へのお問い合わせもLINEでのお問い合わせに次いで多いです。
地方で塾や教室開業される方は固定電話は導入しておいた方がいいと思います。
Wi-Fiと固定電話利用のセットでも6000円ですから、そこまで負担が大きいわけではありません。
携帯電話の掲載をやめて固定電話を導入した理由としては、
- 保護者の方がお問い合わせしやすくなる (携帯ってなんだかお問い合わせしにくくないですか?)
- 業者からの電話が煩わしい
- 個人情報を掲載したくない
- 保護者の方と個人のLINEを交換するのが嫌だから
- 営業時間以外に対応したくない
です。
意外とご自身の携帯番号を掲載している塾や教室さんを見かけるのですが、個人情報がダダ漏れの状態ですので、固定電話を導入するといかがでしょうか?
電子メール
まれに電子メールへもお問い合わせが来ます。
長文でのお問い合わせの方が電子メールでお問い合わせしてくださる傾向にあります。
あってもなくても良いお問い合わせ方法だと思います。
ごくごく稀に塾のInstagramへもお問い合わせがきます。
塾のInstagramをたまに投稿してて、投稿文の一番最後に、
「Instagramでのお問い合わせも可能です」の一文を書いています。
そのためか、
Instagramへお問い合わせをしてくださる方は塾のInstagramの投稿をお読みになってご連絡くださる方が多いようです。
このような一文を毎回の投稿に掲載しています。
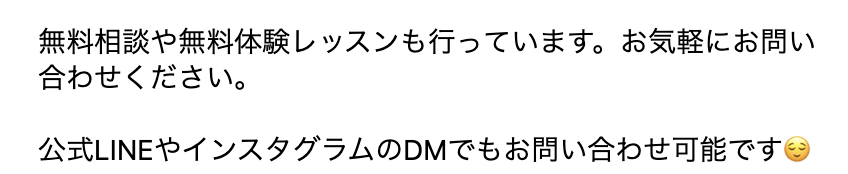
LINE・電話・お問い合わせフォームさえ用意しておけば間違いない
きくらげの塾では
- 固定電話
- webお問い合わせ
- メール
- LINE
- SNS
のように多くのお問い合わせ手段を用意していますが、基本的には
- 固定電話
- webお問い合わせ
- LINE
さえ用意しておけば大丈夫です。
お問い合わせ方法の選択肢が多くても保護者の方を迷わせてしまうだけですし...
多ければいいわけでもありまえんからね。
今回の記事の整理
塾や教室を開業する際、保護者からのお問い合わせ方法の設計は非常に重要です。
お問い合わせ方法の選定にあたっては、保護者が問い合わせしやすいかと自分がやりとりしやすいかの両方を満たすものを選ぶことがポイントです。
きくらげ塾では以下の5つの方法を採用しています。
- 公式LINE
メインのお問い合わせ手段で、全体の5割以上がLINE経由です。使い慣れており、記録が残るためミスを防げます。友達登録者数が増えると信頼感も向上します。 - 固定電話
地方では固定電話への信頼感が高いため、LINEに次いでお問い合わせが多いです。携帯番号の公開に抵抗がある場合、固定電話の導入がおすすめです。 - HPお問い合わせフォーム
シンプルで定番の方法です。営業メールも届くため、フィルタリングが必要ですが、公式LINE導入前はメインの手段でした。 - 電子メール
長文のお問い合わせに利用されることがありますが、頻度は少なめです。 - Instagram
投稿を読んだ方からの稀な問い合わせがあります。投稿に「Instagramでのお問い合わせも可能」と記載することで誘導可能です。
基本的には固定電話、公式LINE、HPお問い合わせフォームの3つがあれば十分です。
保護者が安心して問い合わせられる仕組みを作りつつ、自分の働きやすさも考慮して選定しましょう。
問い合わせ方法を整えることが、入塾につながる大切な第一歩です。
今回の記事はここまでです。

