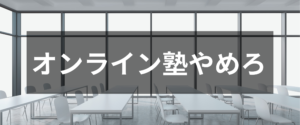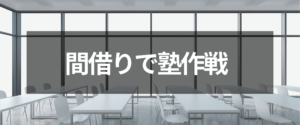どーも、きくらげ鰹です。
本ブログについて
高専専攻科を卒業後、少子高齢化が深刻な人口10万人ちょいの片田舎で、就職もせずに個人塾を開業したきくらげ鰹(カツオ)が書くブログ。金なし・社会人経験ゼロで起業したため、開業時から失敗しまくり。運だけはいいので、従業員ゼロ・家賃3万(笑)のアパート塾で気付けば月収100万(月商130万)の塾に成長。過去の自分へ向けて『月収100万円の安定収入を確立し、満員御礼を継続するための小ネタやノウハウ』をまるでメッセージを送るかのようにして記事を執筆中

よっしゃ! 塾を開業してやるぜ〜。ふむ、開業するには開業届なるものを税務署に出せばいいのか。
と決意して、何も考えずに税務署に開業届を出したきくらげ。
開業手続き自体は所定の書類を税務署に提出するだけなので簡単です。
しかしですね....
何も考えずに開業届を出すと少し面倒ごとになるわけですよ。
とてもとてもめんどいことになったわけです。
生徒が一人入るまで開業届は出さないほがいい
開業届は原則いつまでに出すの?
基本的には、開業する際に収入の有無に関わらず所轄の税務署に開業後1ヶ月内に開業届を出さないといけません。
開業届とは個人事業主として事業を始めることを所轄の税務署に知らせるための書類です。
- 事業所を管轄する税務署の窓口に直接提出する
- 郵送で提出する
- e-Taxや会計ソフトを使ってオンラインで電子申請する
などの方法で税務署に事業を正式に開始したことを知らせることができます。
青色申告を行う予定がある場合は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。
(簡単な開業届と後ほど解説します。青色申告承認申請書)
税法上は個人で事業をやっている場合は開業届を出さないといけません。
所得税法を引用すると...
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
このようにあります。
事業の実態の解釈って人それぞれでは??
しかしですね...
・集客が全くできていない
・HPもインスタグラムもない
・生徒がゼロ
の場合だと、事業の実態がないのと同義だと個人的には考えています。

どの程度のやっていれば事業なのかは個々人によって解釈が違います。経費への考え方も同じなんですよ。売上に直結する / 間接的に直結するのが経費として計上できるのが日本の法律で、これが経費になる / 経費にならないの決まりはありません。
つまり、
・集客が全くできていない
・HPもインスタグラムもない
・生徒がゼロ
で、開業したと言えるのか?
という話になるわけです。生徒が入るまで事業の実態はないと解釈してもいいではないでしょうか。
仮に開業届が遅れてからといってペナルティーはありません。
(多くにフリーランスの人たちは開業届出してないのではないのかな...と思ったり)
開業届を出すメリットして、以下の3点が挙げられますが....
小規模で塾を運営する場合はあまり大きなメリットとはいえませんよね。
①屋号名義の銀行口座が開設できる
開業届を提出すると、屋号名義の銀行口座を作ることができます。個人用の口座を事業用として使うことも可能ですが、屋号名義の口座を利用すると取引先からの信頼が得やすくなります。
①職業の証明になる
開業届の控えは、職業を証明する書類として使えます。たとえば、クレジットカード発行の手続きで職業証明が必要な場合、開業届の控えが役立ちます。会社員が社員証や在職証明書を使うように、個人事業主は開業届の控えを職業証明として使えます。
①公的な支援制度への申請が可能
補助金や助成金などの公的支援制度に申請する際には、開業届の控えが必要になる場合があります
それよりも開業届を急いで出すデメリットの方が大きいかなと思います。
開業届のデメリットときくらげの面倒ごと
会社員から塾を開業する場合は、
① 失業手当が受けられなくなる
というデメリットがあります。
開業届を提出すると、失業手当を受け取る資格を失います。これは、開業届が「事業を開始した」という届け出となり、求職者ではないとみなされるためです。失業手当を受ける予定がある場合は、開業届の提出時期に注意しないといけませんよ。
② 扶養から外れる可能性がある
被扶養者が開業届を提出して個人事業主になると、扶養者が加入している健康保険組合の規定により、被扶養者の資格を失う場合があります。扶養から外れることで保険料の負担が増える可能性があるため、事前に扶養者が加入している健康保険組合の条件を確認しておくことが大切です。
などのデメリットが挙げられます。
そして、そして、最大のデメリットは、
売上0でも確定申告をしないといけないことです。
きくらげの場合は就職せずに塾を開業してやると決めてから何も考えずに開業届を出しました。
開業届を出したのが10月でした。
そうなると、収入がゼロにも関わらず、12月までの売上を確定申告をしなければならなかったのです。
学生でアルバイト収入(給与収入)があって、でも事業収入はない状態での確定申告...
正直何をしていいのかさっぱりなわけです。

いや...あのときは本当に苦労しました。開業届は事業を始めて1ヶ月以内に出せと書いてあったのですぐに出しに行きました。でも、よくよく考えると、HPもない、インスタも開設してない、何を教えるのかも決めてない状態で開業届を出したのは失敗だったなと思います。
無収入なので確定申告をしなくても問題はないのですが、無収入でも開業届を出しているのであれば確定申告はしたほうがいいとされています。
ですので、開業届を出すのはHPやインスタグラム、チラシなどを作り塾運営をする際に必要な作業が全て終わってさらに生徒が一人入塾したタイミングで全然問題ないときくらげは考えます。
(きくらげは税の専門家ではないですので、詳しいことは税理士や税理スタッフにご相談ください)
開業前であれば開業費として計上できるのもお得
さらに、開業届前に支払ったものは全て開業費として扱うことができます。
開業費(かいぎょうひ)とは、新たに事業を始める際に発生する準備活動の費用を指します。具体的には、事業開始前の広告費、設立準備に伴う手数料や交通費、打ち合わせの費用など、開業するまでにかかった費用が対象です。
開業費にすることで、事業開始後に一定期間内で分割して費用計上することが可能です。
※税務上は「任意償却」が認められており、一括償却することも可能です。
つまりですね...
開業届を税務署に提出する前に使った経費はいつの年の経費にしてもいいんですよ。
原則経費はその年度で計上します。
例えば、2024年の机を10万円買った場合は、2024年度の経費として計上しますので、2025年度の経費として計上することはできません。
しかし、開業費であれば、2024年度でも2025年度でも2026年度でもいつ経費にしてもいいのです。
僕は利益が上がった年に開業費約100万円を一括で償却しました。
つまり、
利益=売上-経費-開業費
となり、この利益に対して税金がかかるので...売上状況に合わせて開業費を計上すると税金の額をコントロールすることができます。
(トータルで払う税金の金額は変わらないのですが、お金の流れをコントロールすることができます)
開業費にできるもののリストを以下に書きます。
ちなみに、開業費はこれが開業費だと定められていません。
業務上必要なものは開業費として扱うことができるのです。
事業準備に関する費用
- 開業の広告宣伝費(チラシ、広告、看板作成費用など)
- 名刺作成費
- ホームページやロゴ制作費
手続きに関する費用
- 登記費用(法人の場合)
- 弁護士や司法書士への報酬
- 許可申請や届出にかかる費用
設備・オフィス関連費用
- 内装工事費(ただし一部は固定資産扱い)
- 家具・備品購入費
- 賃貸契約の保証金や礼金(資産として計上する場合も)
人材関連費用
- 採用活動の費用(求人広告、面接交通費など)
- 研修費用
その他
- 交通費
- 打ち合わせ費用
- 開業に伴う調査費
要するに、
① 開業届を出す前に必要なものは全て買う
② 生徒が入れば開業届を出す
をすると、面倒なことにならず、税金面でもメリットがありますよ
ということなのです。
開業届はFreeeで一撃
まずは開業届の提出の流れについて解説します。
開業届を作成する
- 税務署窓口や国税庁のサイトから開業届を入手し記入します。
- 手書きの場合、提出用と控えの2部を用意。
- e-Taxで提出する場合、利用者識別番号を取得してパソコンで入力します。
▼ 開業届は国税庁のサイトから入手できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
税務署に提出する
- 方法1: 税務署窓口で提出し、その場で控えを受け取る。
- 方法2: 必要書類を郵送し、返信用封筒と切手を同封して控えを受け取る。
- 方法3: e-Taxでオンライン提出(控えは発行されず、データを保存)。
控えを保管する
- 窓口または郵送で提出した場合、控えを確実に保管。
- e-Taxの場合、送信データや受信通知を控えとして保存。
が一般的な流れですが、
個人的にはFreeeで開業届を作るのがおすすめです。
きくらげはfreeeを使ったよ
当時は国税庁のサイトから開業届のフォマーマットを確認しても、何を記入していいのかわかりませんでした。
そこで、freee開業を使って開業届を作成しました。
https://www.freee.co.jp/opening
無料で利用でき、指示に従って開業届を作成することができたので、とても簡単です。

出典 : freee 開業
上の画像のように、必要事項を記入していけば、開業届ができます。
freee開業の使い方は、きくらげが解説するよりも
指示にしたって必要事項を記入すれば、開業届が出来上がるので割愛します。

きくらげは学生時代に開業届を作成しました。社会人経験が皆無の学生でも作ることができたので、freeeを使えば開業届は楽に作成することができます
開業届を作成したら、その他必要書類を集めて近くの税務署に提出しに行きました。
今回の記事の内容の整理
個人塾や習い事の教室を開業しようと決めても、すぐに開業届は出さないでくださいね。
失業保険が受け取れなくなったり、売り上げがゼロなのに確定申告をしないといけないはめになります。
・教える科目や仕組みを考える
・必要な機材や物品を揃える
・HPやインスタグラムの開設をする
・チラシなどを配布する
・生徒が1名集まる
・開業届の提出
この段階で、開業届を出すくらいでちょうどいいです。
そして、開業届は、freee開業で作成すると、迷うことなくすぐ作成することができます。
開業届だけではなく
事業開始から2ヶ月以内に
青色申告承認申請書
を提出しないといけません。
俗にいう
白色申告・青色申告
というやつです。
青色一択
だけ伝えておいます。
これの解説はまた次回の記事にしますね。
本ブログ記事はここまでです。