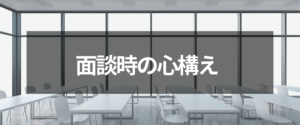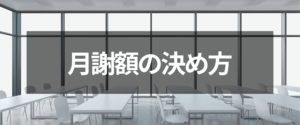どーも、きくらげ鰹です。
本ブログについて
高専専攻科を卒業後、少子高齢化が深刻な人口10万人ちょいの片田舎で、就職もせずに個人塾を開業したきくらげ鰹(カツオ)が書くブログ。金なし・社会人経験ゼロで起業したため、開業時から失敗しまくり。運だけはいいので、従業員ゼロ・家賃3万(笑)のアパート塾で気付けば月収100万(月商130万)の塾に成長。過去の自分へ向けて『月収100万円の安定収入を確立し、満員御礼を継続するための小ネタやノウハウ』をまるでメッセージを送るかのようにして記事を執筆中
塾を開業するときにはあわせてホームページも制作した方がいいです。
ホームページ制作のスキルや知識がある人は自分で作ってもいいでしょう。全くスキルや知識がない人はウェブデザイナーに制作を依頼し方がいいです。
今の時代、10万円で綺麗なホームページが作れる時代ですからね! 数年〜十数年使うと考えれば安い買い物です。
ホームページ制作の経験やウェブデザイナーにホームページ制作の経験がない人は、
「お金さえ払えば、一からホームページを全て作ってくれる」
と思いがちですが、
ホームページの構成や文章は発注者側が用意しなければいけません。
※ もちろん、デザイナーがホームページの構成や文章作成をやってくれる場合もありますが、割高になりやすいです。ディレクターとライターへの外注が必要になるからです。
初めてホームページをウェブデザイナーに発注する個人塾や教室経営者は予算がそこまで捻出できない人もいるかと思います。
ですので、これだけ書いておけばいいよっていうのを本記事で解説します。
塾や教室のホームページに入れた方が良い項目
では、個人塾や個人教室のホームページに最低限盛り込んだ方がいい内容について書いていきます。
1. トップページ
トップページとはサイトを訪問した際に一番初めに出てくる画面です。
きくらげのブログの場合は↓がトップページになります。

トップページの中で上部(画像+文字)をメインビジュアルといいますが、このメインビジュアルは画面が切り替わらないタイプでもいですし、画面が切り替わるタイプでもいいと思います。
※ 画面が切り替わるモードをカールスライドーといいます。
きくらげのブログは画面が切り替わらないタイプにしていますが、塾のホームページは画面が切り替わるタイプにしています。
この最初のメインビジュアルでホームページから離れる人もいるので、きちんとした作り込みが必要になります。
メインビジュアルに入れる項目は
- キャッチコピー: 塾の特徴や強みを端的に表現した一文(例:「少人数指導で成績アップをサポート!」)
- 塾の概要: 「どんな塾か」を簡潔に紹介する文章。ターゲット層や指導のスタイルなどを含めます。
- アクセスボタン: すぐに「問い合わせ」や「料金プラン」を見たい保護者のための目立つリンクボタンを配置します。
といいですね。
きくらげのHPの例だと、キャッチコピーが
一人教室で月収100万円の安定収入と満員御礼を継続するための小ネタ集
です。
その下にある「公式LINEはこちらをCLICK」がアクセスボタンです。
トップページ以外は...
きくらげのブログで、
- 集客
- 教室運営・指導法
- 講師
- 雑記
になっているところを
- 指導のこだわり(教育理念、〇〇塾の指導について、実績)
- 受講料
- 講師紹介
- アクセス情報
- お問い合わせ (無料体験授業)
などのページに飛べるようにするといいはずです。
何を入れて、何を外すかはお任せしますが、
- 指導のこだわり(教育理念、〇〇塾の指導について)
- 受講料
- 講師紹介
- アクセス情報
- お問い合わせ (無料体験授業)
- ブログ
などを入れておけば問題はありません。

1. 指導のこだわり
指導のこだわりページは色々な表現の仕方があります。
- 指導のこだわり
- 塾の特徴
- 〇〇塾の指導
- 教育理念
- 〇〇塾のすごいところ
- 〇〇塾メソッド
などなど、
ご自身がいいなと思う表現に変えてもらえればと思います。
塾のホームページで「指導のこだわり」を伝えるページは、塾の特徴や価値を保護者や生徒に強くアピールする重要な役割を持ちます。このページで最も大切なことは、「あなたの塾ではないとダメな理由」を伝えることです。
以下に、このページに入れておきたい内容を詳しく解説します。
① 教育理念について
何を伝えるか:
塾が大切にしている教育方針や価値観、どのような想いで生徒と向き合っているのかを具体的に記載します。
- 例: 「生徒一人ひとりの可能性を引き出し、将来に繋がる力を育てます」
- 「成績だけではなく、生徒の人間力を伸ばす指導を心がけています」
ポイント:
保護者に「この塾なら安心して任せられる」と思ってもらえるよう、真摯な想いを伝えることが大切です。
② 代表挨拶
何を伝えるか:
塾長自身の想いや経歴を伝えることで、信頼感や親近感を生み出します。顔写真を添えることで、さらに安心感を与えられます。
- 例: 「なぜこの塾を開業したのか」「どのような指導を目指しているのか」を簡潔に説明。
- 「〇〇大学で教育学を学び、子どもたちの成長を支えたいという想いから開業しました」など。
ポイント:
・保護者は「どんな人が教えてくれるのか」に敏感です。塾長自身の人柄や熱意をしっかり伝えましょう。
・肩書や経歴が信頼感につながる場合は積極的にアピール。
③ 指導カリキュラムについて
何を伝えるか:
塾の指導方法やカリキュラムの特長、成績向上に繋がる理由を具体的に説明します。他塾との差別化を意識することが重要です。
- 例: 「全科目の基礎を徹底的に固める独自のメソッド」
- 「授業後のフォローが充実しており、分からない問題はその場で解決」
ポイント:
・他塾では提供できない独自の強みをアピールしましょう。
・具体的な指導例や成功事例を交えると説得力が増します。
④ 塾の魅力(〇〇塾のすごいところ)
何を伝えるか:
保護者や生徒に「この塾を選ぶメリット」を伝える内容です。他では得られない体験や成果を強調します。
- 例: 「少人数制だから、先生が全生徒を徹底サポート」
- 「地域トップの合格実績」「質問しやすい環境」
ポイント:
・具体的な数字やエピソードを活用して信頼性を高める。
・保護者が「自分の子どもに合いそうだ」と感じる要素を意識する。
あとは、必要に応じて入れた項目をどんどんと盛り込んでもらえればこのページは完成です。
3. 受講料
塾のホームページに受講料金を掲載するかどうかで悩む塾経営者もいますが、基本的には受講料金を明記したほうが良いです。
その理由や具体的な記載内容について解説します。
受講料金を明記する理由
① 透明性が信頼感につながる
保護者が最も気にする要素の一つが受講料金です。料金が記載されていないと、「問い合わせをしないとわからない」「高額なのでは?」といった不信感を与える可能性があります。事前に受講料を明確にすることで、安心感と信頼感を与えることができます。
②問い合わせの手間を減らせる
料金が分かれば、保護者は「予算内だから検討しよう」と判断しやすくなります。これにより、不要な問い合わせが減り、本当に興味を持っている保護者からの連絡に集中できます。
実際に受講料金をホームページに書いていても、受講料について教えて欲しいとお問い合わせが来ます。
「いや、HP書いてあるけどな...」と思いながら渋々返信しています...
ホームページに書くべき受講料金の項目
① 学年別・コース別の料金
小学生、中学生、高校生ごとに料金を明記します。複数のコースがある場合は、それぞれの内容と料金を分かりやすく記載します。例 「小学生(週2回コース)月額: 18,000円」「中学生(受験指導)月額: 25,000円」
② 追加費用の説明
入会金、教材費、施設利用料など、授業料以外にかかる費用があれば必ず記載します。例 「入会金: 10,000円」「教材費: 年間12,000円」
③ 料金体系の補足
授業の回数や時間による違いがある場合、その詳細も書きましょう。例えば「週1回(60分)の場合」や「週3回(90分)の場合」など。
値上げ時の対応
料金を値上げする場合も、ホームページで丁寧に説明することが大切です。
① 値上げの理由を明記する
値上げの背景を正直に伝えることで、保護者の理解を得やすくなります。例えば、物価上昇、指導環境の改善、新カリキュラムの導入など。
② 具体的な期日を記載
値上げがいつから適用されるか、はっきりと書きましょう。
例: 「2025年1月より、指導内容の拡充のため、受講料金を以下の通り改定いたします。2024年12月までにご入塾いただいた方は旧料金が適用されます。」
③ 保護者への誠実な対応
値上げ情報は「お知らせページ」に掲載するだけでなく、保護者に直接お伝えするのも重要です。メールや公式LINEで事前に通知すると、信頼感が高まります。
行動経済学のある研究では、値上げの際になんでもいいから理由書いとけば納得されやすいとあります。値上げする場合は理由とけて書いておけばいいです。
ちなみに、きくらげが値上げしたときは、「自習室拡張」「高校生の負担増」により値上げとなります。と書きました。
信頼関係がきちんとしていれば、「先生、受講料あげなくて大丈夫ですか?」と逆に心配されます。
4. 講師紹介
保護者の方が体験授業や申し込みを検討する際、まず気になるのが「誰が教えるのか」という点です。
そのため、講師紹介ページは信頼を得るために非常に重要な役割を果たします。このページを通じて、講師の人柄や指導力を伝えることで、保護者の安心感と期待を高めることができます。
講師紹介ページに掲載すべき基本情報
以下の内容は必ず書くようにしましょうね。
① 氏名
講師の名前をフルネームで記載します。親しみやすさを持たせるために、ニックネームや呼び名を併記するのも効果的です。
② 学歴
出身中学、高校、大学(専攻)などを記載します。指導に関連する学歴をアピールすることで信頼感を高められます。例:「〇〇大学教育学部卒業」「△△高校出身」
③ 資格
教育や指導に関する資格を明記しましょう。特に英検や教員免許、専門資格があれば信頼度がさらにアップします。「中学校教諭一種免許」「英検準1級」「TOEIC 900点」
④ 指導科目
自分が担当する教科や得意分野を具体的に書きます。「高校数学・物理」「中学英語・国語」
⑤ 趣味や特技
講師の人柄を伝えるために、趣味や特技を記載しましょう。親しみを感じてもらいやすくなります。「趣味: 読書、ハイキング」「特技: ピアノ演奏」
⑥ 顔写真
信頼感を与えるために、プロのカメラマンによる明るく清潔感のある写真を掲載します。適切な表情や服装で撮影した写真が望ましいです。
ページをさらに魅力的にするための工夫
① 指導への想いを書く
「どんな想いで生徒と向き合っているのか」「教育を通じて何を目指しているのか」を記載します。これにより、講師の真剣さや熱意が伝わります。「生徒一人ひとりに寄り添い、成績だけでなく自信を育てる指導を心がけています。」「勉強の楽しさを伝え、『できる』という達成感を生徒と共有したいです。」
② 講師としてのストーリーを加える
「どうして塾講師を志したのか」「これまでの指導経験で印象深かったエピソード」などを簡単に記載すると、より人間味が伝わります。
③ 生徒や保護者からの感想を掲載
実際の生徒や保護者からの声を引用することで、信頼性がさらに高まります。「授業が分かりやすく、子どもが数学を好きになりました!」(保護者の声)
5. アクセス情報
アクセス情報はまずはGoogle マップは必ず埋め込みましょう。
〇〇中学から自転車で〇〇分、〇〇駅から徒歩何分など自転車や徒歩でのアクセス情報があると便利です。
さらには駐車場の情報も載せておくといいですね。
6. お問い合わせ (無料体験授業)
お問い合わせフォームを設定する
お問い合わせフォームは、保護者が気軽に問い合わせできるツールです。ウェブデザイナーに以下の内容を伝え、シンプルで使いやすいフォームを設置してもらいましょう。
フォームに必要な項目
- 保護者の名前(または生徒の名前)
- 連絡先(メールアドレスや電話番号)
- お問い合わせ内容(テキストボックス)
- 希望コースや学年(選択式)
- その他(自由記述欄)
★ ポイント
- 必要最低限の項目にすることで、記入の手間を軽減します。
- 送信後の確認メッセージや、自動返信機能を設定しておくと親切です。
2. 入塾までの流れを記載
お問い合わせページに「入塾までの流れ」を掲載すると、保護者や生徒が次に何をすれば良いのかが明確になります。特に、初めて塾を利用する保護者にとって安心材料となります。
例: 入塾までの流れ
- お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。ご質問や不明点があればお気軽にどうぞ。 - 体験授業の予約
希望日時を調整し、体験授業を受けていただきます。実際の授業の雰囲気や指導内容をご確認ください。 - 体験授業の実施
実際の授業を通じて、お子様に合うかどうかを判断していただきます。 - ご相談・お申し込み
授業後に保護者の方とご相談の時間を設けます。納得いただけた場合は、入塾手続きを行います。 - 授業開始
入塾後、初回授業の日程を決定し、本格的に授業がスタートします!
7. ブログやお知らせ
保護者の方は、子どもを通わせる塾を決める際に、ホームページのブログをしっかりチェックする傾向があります。
最近では、子どもが小さいうちから未来を見据えて塾をリサーチする家庭も増えています。有益な情報を発信することで、保護者に「この塾に通わせたい」と思わせることができます。
きくらげの塾でもブログはたまに書いています。
その結果
「ブログ見ています」
「先生のブログはとても勉強になります」
などのお声をいただくことが多いです。
ブログを書くことで、保護者の方にあなた自身を知ってもらえって入塾に結びつけたり、入塾後の退塾を防止することができます。
本記事の整理
個人塾のホームページは、塾の第一印象を決める重要な役割を果たします。
必要な内容をバランスよく盛り込み、透明性や信頼感を意識して作成することで、保護者や生徒に「この塾に通いたい」と思わせるホームページを作ることができますよ。
1. トップページ
サイトを訪れた際に最初に目にする画面です。キャッチコピー、塾の概要、アクセスボタンを配置し、塾の魅力が一目で伝わるように作り込みましょう。特にメインビジュアルの完成度が重要で、視覚的に魅力的なページが訪問者の滞在率を高めます。
2. 指導のこだわり
塾の教育理念や指導方針を伝えるページで、「この塾でなければならない理由」を明確に示すことがポイントです。教育理念、代表挨拶、指導カリキュラム、塾の魅力を盛り込み、他塾との差別化をアピールしましょう。
3. 受講料
受講料金は明確に記載することが信頼感につながります。学年別・コース別料金、追加費用、授業体系などをわかりやすく書き、透明性を保ちましょう。また、値上げ時は理由と適用時期を丁寧に説明することが大切です。
4. 講師紹介
保護者が最も気にする「誰が教えるのか」を詳細に記載します。氏名、学歴、資格、指導科目、趣味、顔写真を明記し、指導への想いや経歴を具体的に伝えましょう。人柄が伝わるストーリーや生徒・保護者の声を添えると信頼感が増します。
5. アクセス情報
Googleマップの埋め込みや、最寄り駅や中学校からの距離、自転車や徒歩でのアクセス情報を記載しましょう。駐車場の有無も書くと、保護者にとって便利な情報となります。
6. お問い合わせ
お問い合わせフォームはシンプルかつ使いやすいものにし、名前、連絡先、問い合わせ内容などの項目を設けます。また、入塾までの流れを掲載することで、保護者が次に何をすればよいかが明確になります。
7. ブログやお知らせ
ブログやお知らせは塾の魅力を発信する重要なツールです。教育に役立つ情報や塾の日常、成功事例を定期的に更新することで、保護者との信頼関係を築きやすくなります。
今回の記事はここまで